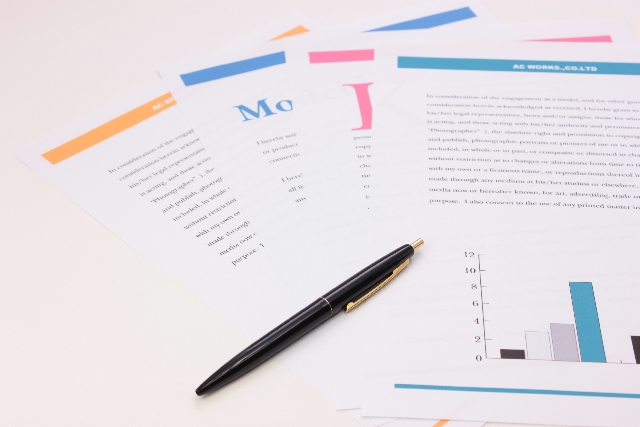


傷病手当について。
傷病手当
私は昨年4月に新卒で入社した23歳の女です。
最近、人間関係でのストレスや将来への不安から
仕事中でも休日でも異常な目眩と多汗、嘔吐が続いています。
1ヵ月前から心療内科に通い、『パニック傷害』と診断されました。
今はパキスルとデパスを飲みながら、何とか生活はできていますが、
デパスの効き目が切れるとテレビや本、ラジオ、ケータイも何をやっても
頭に入ってこないでボーッとしてその後不安感でパニック発作が多くなりました。
母が昔、鬱病だったこともあり、父親は「仕事はいつでもできるから
今は早く休んだ方が良い」と胃ってくれています。医者も同様です。
そこで本題なのですが、もし今年の3月末まで仕事をして、(年度末で忙しいので)
4月末までの1ヶ月間傷病手当をもらいながら休職し、
その後すぐ退職しでも傷病手当を続けて頂けますか?
被保険者1年以上になるために、その休職の1ヵ月の期間は
被保険者期間に入るのでしょうか?
保険証ではH22年4月7日付けで交付されていますが、
実際に保険料を引き落とされたのはH22年5月末です。
よく自分でも分からないのでどなたか知識を貸して下さい。お願いします。
傷病手当
私は昨年4月に新卒で入社した23歳の女です。
最近、人間関係でのストレスや将来への不安から
仕事中でも休日でも異常な目眩と多汗、嘔吐が続いています。
1ヵ月前から心療内科に通い、『パニック傷害』と診断されました。
今はパキスルとデパスを飲みながら、何とか生活はできていますが、
デパスの効き目が切れるとテレビや本、ラジオ、ケータイも何をやっても
頭に入ってこないでボーッとしてその後不安感でパニック発作が多くなりました。
母が昔、鬱病だったこともあり、父親は「仕事はいつでもできるから
今は早く休んだ方が良い」と胃ってくれています。医者も同様です。
そこで本題なのですが、もし今年の3月末まで仕事をして、(年度末で忙しいので)
4月末までの1ヶ月間傷病手当をもらいながら休職し、
その後すぐ退職しでも傷病手当を続けて頂けますか?
被保険者1年以上になるために、その休職の1ヵ月の期間は
被保険者期間に入るのでしょうか?
保険証ではH22年4月7日付けで交付されていますが、
実際に保険料を引き落とされたのはH22年5月末です。
よく自分でも分からないのでどなたか知識を貸して下さい。お願いします。
退職後も傷病手当金を受給するためには、次の全ての要件を満たす必要があります。
1.退職日に1年以上継続して健康保険の被保険者であること。
2.在職中に傷病手当金を受給しているか受給要件を満たしていること。
3.退職日以後も在職中から引続き私傷病により労務不能の状態であること。
4.退職日に傷病手当金の支給が開始されてから1年6ヶ月未満であること。
1に関しては、健康保険証の「交付日」ではなく、「資格取得日」をご覧下さい、その日付が平成22年4月1日となっていれば、平成23年3月31日でちょうど1年となりますので、平成23年4月30日に退職予定であれば、1の要件を満たすこととなります。
2に関しては、4月1日~4月31日まで休職し、傷病による労務不能期間が出来るならば、第1回目の傷病手当金の申請手続きが退職後となっても、退職後も引き続き傷病手当金を受給することが可能です。
3に関しては、退職日は必ず傷病により欠勤状態にし、出社しないことです。
以上が実行出来れば、退職後であっても在職中の傷病手当金の支給開始後最長1年6か月傷病手当金を受給することが可能となります。
【補足について】
まず、退職後30日経過後1か月以内に、ハローワークで「受給期間延長申請」を行います。傷病手当金の受給が終了し、就労可能となれば、医師に「就労可能証明書」を書いてもらい、離職票その他の必要書類持参で、ハローワークで「受給期間延長」を解除し、求職の登録と失業手当(基本手当)受給手続きをとれば、求職活動しても再就職先が決まらない場合、最長90日分の失業手当が給付されます。
1.退職日に1年以上継続して健康保険の被保険者であること。
2.在職中に傷病手当金を受給しているか受給要件を満たしていること。
3.退職日以後も在職中から引続き私傷病により労務不能の状態であること。
4.退職日に傷病手当金の支給が開始されてから1年6ヶ月未満であること。
1に関しては、健康保険証の「交付日」ではなく、「資格取得日」をご覧下さい、その日付が平成22年4月1日となっていれば、平成23年3月31日でちょうど1年となりますので、平成23年4月30日に退職予定であれば、1の要件を満たすこととなります。
2に関しては、4月1日~4月31日まで休職し、傷病による労務不能期間が出来るならば、第1回目の傷病手当金の申請手続きが退職後となっても、退職後も引き続き傷病手当金を受給することが可能です。
3に関しては、退職日は必ず傷病により欠勤状態にし、出社しないことです。
以上が実行出来れば、退職後であっても在職中の傷病手当金の支給開始後最長1年6か月傷病手当金を受給することが可能となります。
【補足について】
まず、退職後30日経過後1か月以内に、ハローワークで「受給期間延長申請」を行います。傷病手当金の受給が終了し、就労可能となれば、医師に「就労可能証明書」を書いてもらい、離職票その他の必要書類持参で、ハローワークで「受給期間延長」を解除し、求職の登録と失業手当(基本手当)受給手続きをとれば、求職活動しても再就職先が決まらない場合、最長90日分の失業手当が給付されます。
①~③教えて下さい。病気の為休職し、社会保険の傷病手当金をもらう予定です。
①療養は、実家で過ごしたいですが、転居・転院に伴うと、
休職による傷病手当金か退職による傷病手当、どちらも受給できないですか?
長文になりますので、詳しくは補足で。
傷病手当金と傷病手当、両方を同時に受けることはできないのは、わかっています。
どなたかの質問で、転院で医師記入欄の申請期間に空白があると、傷病手当金は打ち切りになるとありましたので、
①を質問しました。
また、このまま病気が治らないのでは、と不安です。
②傷病手当金満期(1年半)終了後か途中で、復職できず退職になった場合は、雇用保険の傷病手当を受けられますか?
休職が6ヶ月以上に及ぶと、雇用保険の傷病手当が受けられない、とハローワークで聞きました。会社では最大1年半休職させてもらえます(医師の診断書によりますが)
③休職せずそのまま退職、雇用保険の傷病手当をうけた方がよいのでしょうか?
傷病手当金と傷病手当や不安が頭の中でごちゃまぜになり、詳しい人がそばにいないので、
わかりにくい質問かもしれませんが、どうかアドバイスお願い致します。
①療養は、実家で過ごしたいですが、転居・転院に伴うと、
休職による傷病手当金か退職による傷病手当、どちらも受給できないですか?
長文になりますので、詳しくは補足で。
傷病手当金と傷病手当、両方を同時に受けることはできないのは、わかっています。
どなたかの質問で、転院で医師記入欄の申請期間に空白があると、傷病手当金は打ち切りになるとありましたので、
①を質問しました。
また、このまま病気が治らないのでは、と不安です。
②傷病手当金満期(1年半)終了後か途中で、復職できず退職になった場合は、雇用保険の傷病手当を受けられますか?
休職が6ヶ月以上に及ぶと、雇用保険の傷病手当が受けられない、とハローワークで聞きました。会社では最大1年半休職させてもらえます(医師の診断書によりますが)
③休職せずそのまま退職、雇用保険の傷病手当をうけた方がよいのでしょうか?
傷病手当金と傷病手当や不安が頭の中でごちゃまぜになり、詳しい人がそばにいないので、
わかりにくい質問かもしれませんが、どうかアドバイスお願い致します。
転居・転院は傷病手当金の受給資格がなくなる要件にはならないと思います。患者には医師や病院を選ぶ権利がありますから、転院して傷病手当金が止められたのではたまったものではありません。
転院で医師記入欄の申請期間に空白があると打ち切りになるということもないと思います。医師の所見がなければ支払われないです。おそらくは郵送しても突き返されてくるだけではないかと思います。転院して、担当医が変わった場合は、新しい担当医は自分が診察していない期間についてはわからないですから、カルテのコピーを転院先の新しい病院に提出すれば良いでしょう。
ただし、これについては私も考えたことがないというか、治療のために転居するとか転院するいう発想がないので、加入している健康保険組合・協会に問い合わせたほうが良いです。
傷病手当金の受給期間が残っている状態で退職をすると、健康保険組合・協会に継続して1年以上加入していれば、退職後も通算1年半まで傷病手当金を受給することはできます。
傷病手当金の受給期間終了した時点で、まだ担当医の就業許可が下りていない場合には、退職しても失業給付の受給申請はできません。失業給付は仕事ができる状態にあるにもかかわらず、仕事がない方の求職活動を円滑に進められるように支給されるものです。ですので就業できない方の受給申請は認められません。雇用保険の傷病手当は受給資格が認定された後、労務に服することができない状態になった方に支給されるものですから、受給資格の認定がされなければ、受給できません。
病気などで休養して退職した場合には受給期間延長手続きを取ることになります。これは通常離職日の翌日から1年間の受給期間の進行を停止する手続きで、最大3年間延長が可能です。受給期間延長手続きを行った後、医師から就業可能であるとの許可を得られた時点で、延長の終了の手続きを取り、同時に受給申請をすることになります。
また、病気を理由に退職した場合、現行では24年3月31日までに離職した方に限って、特定理由離職者の範囲に当たり、診断書等の病気を理由に退職したことを証明する書類を提出することによって、特定理由離職者として受給認定され、受給資格認定日を含めた7日間の待期期間は免除されませんが、給付制限期間は免除されます。更に、雇用保険の被保険者期間と離職時の年齢により、支給日数が通常の受給資格者よりも長くなる場合があります。
休職期間が6か月以上になると雇用保険の傷病手当を受けることができないという話は、正直言って初めて聞く話です。一応、調べますが、今はちょっとそれについては回答できません。何しろ知らないので。
休職している間でも会社には在籍していますので、その間も会社は一部の社会保険を会社負担分は支払い続けています。また、所得税は5、6月あたりで年間の平均所得を概算で算出して源泉徴収をしていますし、地方税も徴収されているはずです。傷病手当金は本人の指定の口座に直接振り込まれますから、会社がそういったものを天引きすることはできません。今まで会社から社会保険料や税金の支払いを求められていないのであれば、社会保険の本人負担分と税金を肩代わりしていると思われます。その場合、放っておくと結構大きな金額になりますので、毎月本人負担分の社会保険料と税金については会社に支払っておいた方が良いと思います。
あるいは、退職をして、国保・国民年金に切り替え、失業給付の受給期間延長手続きをすれば、税金などの支払いは自分たちで管理することができるので、その方が安全と言うか、安心できるのではないかと思います。会社に無用な社会保険料を支払わせるのも酷ですし、退職をされた方が良いのではないかと思います。退職金の支払い規定に合致すれば退職金も支払われるでしょうし。
会社が許してくれさえすれば就業規則の退職の通告が1か月前であったとしても、12月末での退職にしておけば年末調整されますので、傷病手当金は非課税ですので、還付金があります。また、医療費の自己負担分が10万円を超えていて、医療機関、薬局からの領収書があれば、10万円を超えた部分の1/10は還付されますので、確定申告が必要となります。
なんだか、分かりづらい回答になってしまいました。もともと長文な上に、傷病手当金と退職が絡むと結構面倒なもので。
傷病手当の受給期間が終了しても就業できない場合は、福祉課に相談してみてください。精神疾患であれば国や市区町村の支援について知っていることは多少ありますが、身体的なものであるとちょっとわからないので。
転院で医師記入欄の申請期間に空白があると打ち切りになるということもないと思います。医師の所見がなければ支払われないです。おそらくは郵送しても突き返されてくるだけではないかと思います。転院して、担当医が変わった場合は、新しい担当医は自分が診察していない期間についてはわからないですから、カルテのコピーを転院先の新しい病院に提出すれば良いでしょう。
ただし、これについては私も考えたことがないというか、治療のために転居するとか転院するいう発想がないので、加入している健康保険組合・協会に問い合わせたほうが良いです。
傷病手当金の受給期間が残っている状態で退職をすると、健康保険組合・協会に継続して1年以上加入していれば、退職後も通算1年半まで傷病手当金を受給することはできます。
傷病手当金の受給期間終了した時点で、まだ担当医の就業許可が下りていない場合には、退職しても失業給付の受給申請はできません。失業給付は仕事ができる状態にあるにもかかわらず、仕事がない方の求職活動を円滑に進められるように支給されるものです。ですので就業できない方の受給申請は認められません。雇用保険の傷病手当は受給資格が認定された後、労務に服することができない状態になった方に支給されるものですから、受給資格の認定がされなければ、受給できません。
病気などで休養して退職した場合には受給期間延長手続きを取ることになります。これは通常離職日の翌日から1年間の受給期間の進行を停止する手続きで、最大3年間延長が可能です。受給期間延長手続きを行った後、医師から就業可能であるとの許可を得られた時点で、延長の終了の手続きを取り、同時に受給申請をすることになります。
また、病気を理由に退職した場合、現行では24年3月31日までに離職した方に限って、特定理由離職者の範囲に当たり、診断書等の病気を理由に退職したことを証明する書類を提出することによって、特定理由離職者として受給認定され、受給資格認定日を含めた7日間の待期期間は免除されませんが、給付制限期間は免除されます。更に、雇用保険の被保険者期間と離職時の年齢により、支給日数が通常の受給資格者よりも長くなる場合があります。
休職期間が6か月以上になると雇用保険の傷病手当を受けることができないという話は、正直言って初めて聞く話です。一応、調べますが、今はちょっとそれについては回答できません。何しろ知らないので。
休職している間でも会社には在籍していますので、その間も会社は一部の社会保険を会社負担分は支払い続けています。また、所得税は5、6月あたりで年間の平均所得を概算で算出して源泉徴収をしていますし、地方税も徴収されているはずです。傷病手当金は本人の指定の口座に直接振り込まれますから、会社がそういったものを天引きすることはできません。今まで会社から社会保険料や税金の支払いを求められていないのであれば、社会保険の本人負担分と税金を肩代わりしていると思われます。その場合、放っておくと結構大きな金額になりますので、毎月本人負担分の社会保険料と税金については会社に支払っておいた方が良いと思います。
あるいは、退職をして、国保・国民年金に切り替え、失業給付の受給期間延長手続きをすれば、税金などの支払いは自分たちで管理することができるので、その方が安全と言うか、安心できるのではないかと思います。会社に無用な社会保険料を支払わせるのも酷ですし、退職をされた方が良いのではないかと思います。退職金の支払い規定に合致すれば退職金も支払われるでしょうし。
会社が許してくれさえすれば就業規則の退職の通告が1か月前であったとしても、12月末での退職にしておけば年末調整されますので、傷病手当金は非課税ですので、還付金があります。また、医療費の自己負担分が10万円を超えていて、医療機関、薬局からの領収書があれば、10万円を超えた部分の1/10は還付されますので、確定申告が必要となります。
なんだか、分かりづらい回答になってしまいました。もともと長文な上に、傷病手当金と退職が絡むと結構面倒なもので。
傷病手当の受給期間が終了しても就業できない場合は、福祉課に相談してみてください。精神疾患であれば国や市区町村の支援について知っていることは多少ありますが、身体的なものであるとちょっとわからないので。
精神障害者手帳や生活保護については、作業所の施設長さんが詳しいのですが、土日は休みなため、不安でして。
鬱病での精神障害者手帳の診断書は、精神科の先生がおおげさに書いてくれていました…死にたくなることも。生活については、補助が必要なことも書いてくれました。
生命保険には入っていません。お金については…銀行には喘息の公害認定で振り込まれますが、外出する為のお金で、すぐになくなってしまい、足りない状態です。
こちらは東京で23区内、生活保護をうけるなら家賃は5万以下と教わり、家賃5万以下の物件をサイトで保存してあります。
生活保護については無知で真剣ですので、ご回答宜しくお願いいたします。
精神障害者手帳が3級だとしても、生活保護の相談やうけられる見込みはありますでしょうか?
やはりムリして働かないといけないんでしょうか?
鬱病での精神障害者手帳の診断書は、精神科の先生がおおげさに書いてくれていました…死にたくなることも。生活については、補助が必要なことも書いてくれました。
生命保険には入っていません。お金については…銀行には喘息の公害認定で振り込まれますが、外出する為のお金で、すぐになくなってしまい、足りない状態です。
こちらは東京で23区内、生活保護をうけるなら家賃は5万以下と教わり、家賃5万以下の物件をサイトで保存してあります。
生活保護については無知で真剣ですので、ご回答宜しくお願いいたします。
精神障害者手帳が3級だとしても、生活保護の相談やうけられる見込みはありますでしょうか?
やはりムリして働かないといけないんでしょうか?
こんにちは☆
まず
生活保護の相談や受付は
区役所の管轄です
保健相談所ではやってはもらえないとおもいます
生活保護を受給したいのだとおもうのですが
生活保護というのは「申請」は誰でもできます
しかし申請が受理されるかどうかは
審査にかけられてから決定します
受理される場合の重要な条件をおおざっぱにいいますと
○病気等が理由で就労が不可能な状態にある(医師から就労不能であることの証明が必要)
○無資産である(区役所内で調査)
○身内等からの援助も受けられない(身内に確認がいきます)
⇒要するに「お金を稼ぐことができない状態にあり、換金できるような財産ももっていない。扶養もしてもらえない。目下の生活に困窮している」
このような状態の人で
その事実が証明されれば
申請は受理されて、保護費を受給できるとおもいます
審査の主な対象は、平たくいえば「財産」に関してです
○手持ちの通帳などにある預貯金残金
○家や車やバイクなどの固定資産
○生命保険の解約返戻金等
まぁとにかく洗いざらい調査されます
精神3級のうつ病で生活保護が受けられるかどうか・・・というよりも
「働けない状態かどうか」に焦点があてられるのです
手帳取得は自己申請ですから
実際に障害があっても手帳を持っていない人はいますし
かなりな老人であれば就労不可能は当然ですし・・
ほんとうに就労が不可能で生活保護でなければ生きていけない状態でしたら
真実を証明すればいいだけですから
心配はいらないでしょう
ですが
さっき挙げたような「財産」が
現金ならばだいたい10万円以上、
固定資産ならば特に家やマンションなどを所有している場合には
受理はされません
また
受理されたとしても
申請の日の時点で通帳に残金があったとしたら
それは区役所の没収です
喘息の・・・ということですが
保護を受けるようになれば保護費に障害者加算として等級なりの加算がつきますから
手帳の効果が優先になって
喘息の手当てはどうなるか・・・・・なんとも
そこまでは私にはちょっとわかりませんが・・
とにかく
申請は区役所です
区役所へ行き、
窮状を訴えて申請をしてください
余計なアドバイスかもしれませんが
申請に行く時点で
預貯金残高はすべて0にしておくべきです
手持ちの現金も2万~3万程度が無難です
(1カ月かつかつ食べれる程度)
車やバイクを持っているなら
処分して換金しておくべきです
パソコンやエアコン程度はもっていても大丈夫です
がんばりましょう☆
まず
生活保護の相談や受付は
区役所の管轄です
保健相談所ではやってはもらえないとおもいます
生活保護を受給したいのだとおもうのですが
生活保護というのは「申請」は誰でもできます
しかし申請が受理されるかどうかは
審査にかけられてから決定します
受理される場合の重要な条件をおおざっぱにいいますと
○病気等が理由で就労が不可能な状態にある(医師から就労不能であることの証明が必要)
○無資産である(区役所内で調査)
○身内等からの援助も受けられない(身内に確認がいきます)
⇒要するに「お金を稼ぐことができない状態にあり、換金できるような財産ももっていない。扶養もしてもらえない。目下の生活に困窮している」
このような状態の人で
その事実が証明されれば
申請は受理されて、保護費を受給できるとおもいます
審査の主な対象は、平たくいえば「財産」に関してです
○手持ちの通帳などにある預貯金残金
○家や車やバイクなどの固定資産
○生命保険の解約返戻金等
まぁとにかく洗いざらい調査されます
精神3級のうつ病で生活保護が受けられるかどうか・・・というよりも
「働けない状態かどうか」に焦点があてられるのです
手帳取得は自己申請ですから
実際に障害があっても手帳を持っていない人はいますし
かなりな老人であれば就労不可能は当然ですし・・
ほんとうに就労が不可能で生活保護でなければ生きていけない状態でしたら
真実を証明すればいいだけですから
心配はいらないでしょう
ですが
さっき挙げたような「財産」が
現金ならばだいたい10万円以上、
固定資産ならば特に家やマンションなどを所有している場合には
受理はされません
また
受理されたとしても
申請の日の時点で通帳に残金があったとしたら
それは区役所の没収です
喘息の・・・ということですが
保護を受けるようになれば保護費に障害者加算として等級なりの加算がつきますから
手帳の効果が優先になって
喘息の手当てはどうなるか・・・・・なんとも
そこまでは私にはちょっとわかりませんが・・
とにかく
申請は区役所です
区役所へ行き、
窮状を訴えて申請をしてください
余計なアドバイスかもしれませんが
申請に行く時点で
預貯金残高はすべて0にしておくべきです
手持ちの現金も2万~3万程度が無難です
(1カ月かつかつ食べれる程度)
車やバイクを持っているなら
処分して換金しておくべきです
パソコンやエアコン程度はもっていても大丈夫です
がんばりましょう☆
関連する情報